土壌サンプル採取日
2024年9月11日
土壌診断 項目
1.全炭素量(C)、全窒素量(N)、C/N比
2.菌根共生率、菌根菌胞子数
3.一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数
土壌診断証明書
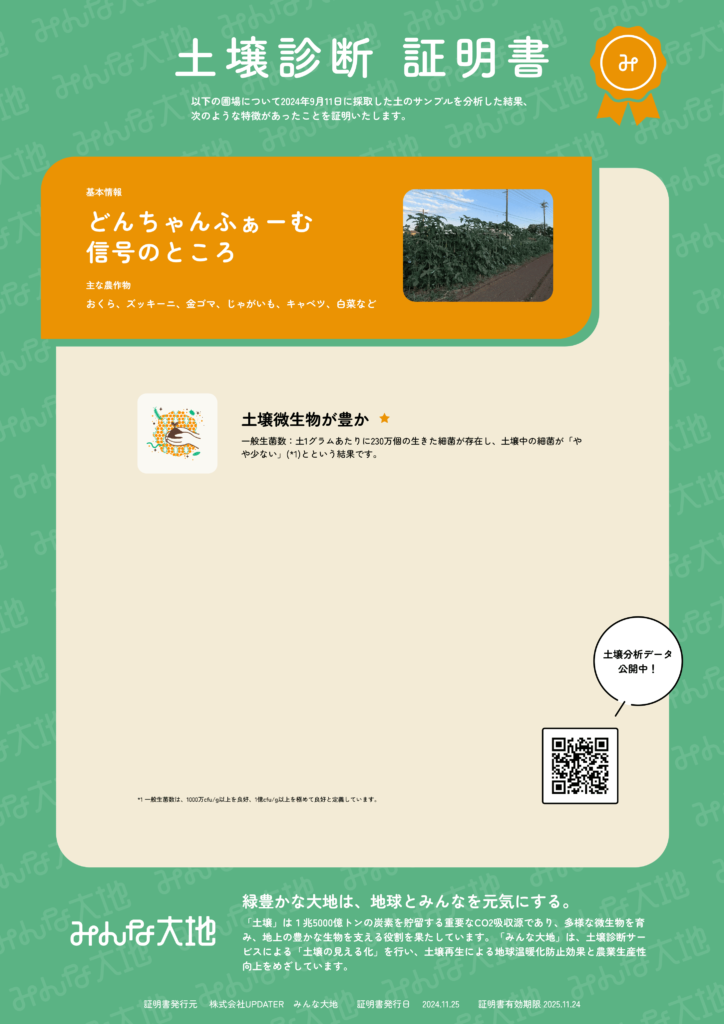
土壌診断レポート
考察
■この圃場の土は「腐植質普通アロフェン質黒ボク土」に分類され、畑地に広く利用される典型的な黒ボク土です。
■今回の検査では、全炭素量が地質標準値(農研機構「土壌のCO2吸収「見える化」サイト」記載値)より23%ほど少ない値でした。要因として、有機転換前に長年続いた慣行栽培により土中の有機物成分が失われたことが考えられます。近年の有機栽培を通して一定量の有機物が土中に戻されつつあるが、未だ十分では無いのでしょう。
■一般生菌数(生きた細菌数)は土1gに230万個でした。有機圃場としてはやや少ないことから、投入した有機物を十分に分解利用できていない可能性があります。
■土壌に炭素が貯まるためには、有機物の分解を担う土壌生態系が機能していることが必要です。その主役は土壌細菌ですので、炭素貯留がやや少なかったことも、土壌細菌の少なさが要因の一つである可能性があります。
■菌根菌はほぼ不在でした。不在の要因は、①過去に使用された農薬の影響が残っている、②過剰施肥により土壌中の無機養分が多い、が考えれます。菌根菌を活用する農法に関心が有れば、不在の要因を排除した上で菌根菌製剤の施用を行うと良いでしょう。
■極めて少量の大腸菌が検出されましたが、公衆衛生上、全く問題になるレベルではありません。
土壌診断結果を受けて(鈴木さんコメント)
土壌診断をした畑は、8年ほど耕作している土地で、その前は地主さんが一部を家庭菜園に使用している程度でした。
借りた当初は牛糞堆肥などを入れていましたが、特に何をしなくても野菜がよく出来る畑だったので、ここ数年は基本的に何も入れず生産していて、途中で生育が怪しくなってきたときは、生ごみ堆肥や米ぬかをいれて微調整していました。畑に生える草は、栽培期間中は刈って畑に敷いていて、持ち出しなどはしておらず、野菜の残渣はすきこんでいます。
今回、有機物や微生物の量がそれほど多くないというデータが出て、これまでは作物がよく獲れていましたが、作物が土地の力を収奪すると考えると、基本的には痩せていくはずなので、これからを見据えて有機物や微生物を増やしていくことは考えていきたいと思います。
また地域には、競争馬を飼育、トレーニングしている業者さんや、乗馬クラブを運営している業者さん、引退馬を引き取って乗馬体験など第二の人生(馬生?)を送る場所を運営している業者さんが沢山あります。そういった場所から出る馬糞を、他の農家さんが堆肥として活用したところ、野菜の生育が良くなったという話を聞きました。飼い主の方は馬糞の処理が課題なので、こういうものも資源として活用できるといいなと思っています。
またここ2年くらい、隣町の小川町の農家さんが、青山在来大豆の出来が悪く困っていて、嵐山町の僕のところではよく獲れるということが起きています。育ちのいいところと悪いところを土壌診断してみると、何かわかるかもしれませんね。


写真)土壌サンプル採取時の信号のところ(2024年09月11日)
