土壌サンプル採取日
2024年9月12日
土壌診断 項目
1.全炭素量(C)、全窒素量(N)、C/N比
2.菌根共生率、菌根菌胞子数
3.一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数
土壌診断 証明書
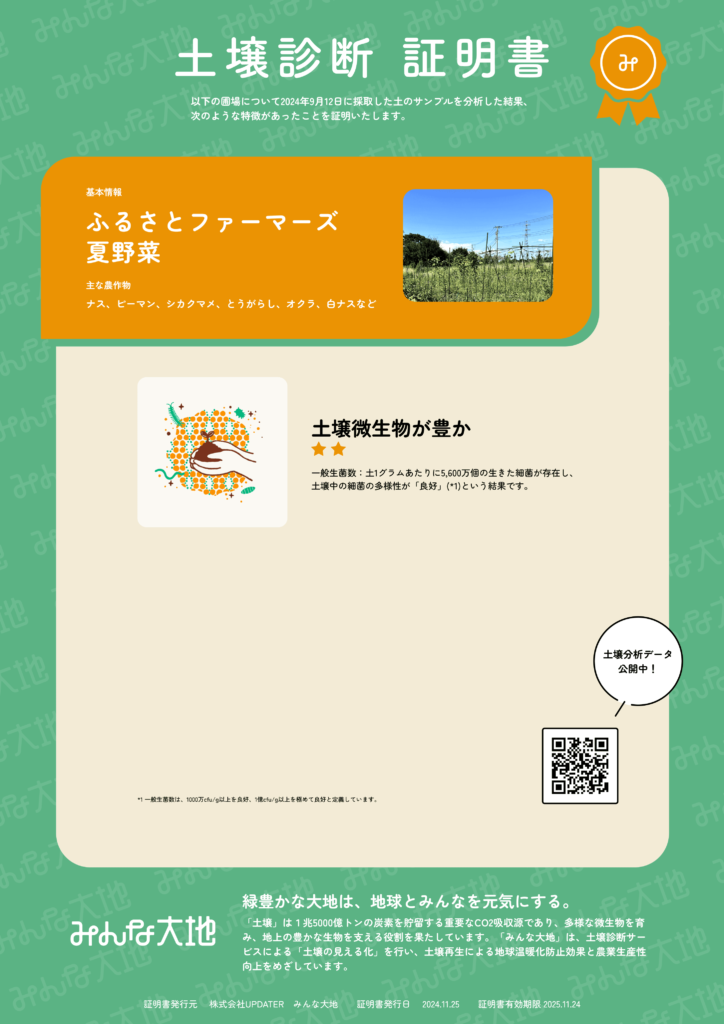
土壌診断レポート
考察
■この圃場の土は「多腐植質厚層アロフェン質黒ボク土」に分類され、畑地に広く利用される典型的な黒ボク土です。
■全炭素量が地質標準値(農研機構「土壌のCO2吸収「見える化」サイト」記載値)より15%ほど少ない値でした。要因として、有機転換前に長年続いた慣行栽培により土中の有機物成分が失われたこと、近年の不耕起栽培を通して一定量の有機物が土中に戻されつつあるが、未だ十分では無いことが考えられます。
■地質標準よりは少ないとは言え、比較的多くの有機物を含むこと、土壌細菌(一般生菌数:土1gに5,600万個)が多いこと、さらに、窒素量も適正範囲にあることから、化学肥料に頼らずに作物生産が可能になる基本条件は整っています。
■菌根菌はほぼ不在でした。要因は、①過去に使用された農薬の影響が残っている、②過剰施肥により土壌中の無機養分が多い、が考えれます。菌根菌を活用する農法に関心が有れば、不在の要因を排除した上で菌根菌製剤の施用を行うと良いでしょう。
■大腸菌は非検出で、病原性細菌による作物汚染リスクは無く、農作業も安心です。
土壌診断診断結果を受けて(石井さんコメント)
土壌をデータで見ることができて、診断してよかったと思っています。
本を読んだり色々調べたりしながら不耕起栽培に取り組んで4年が経ちました。今回のレポートを通して、自分たちが実際にどうしていったらいいのか、明確になりました。
炭素貯留量の現在地を確認することができたし、まだまだ他の畑に比べて足りないこともわかり、菌や土中に対して意識を強めるきっかけになりました。
今後は菌根菌を増やす方法を探したり、落ち葉を入れるなど堆肥の部分で二酸化炭素の固定につなげられるか試してみたいと思います。
私たちはNPOとして活動しています。その中で、こどもたちや企業に対して説明する機会があるので活用させていただきます。
来年以降も定期的に土のデータを取りたいと思いますので、よろしくお願いします。

写真)土壌サンプル採取時の夏野菜(ナス、ピーマン)圃場(2024年9月12日)
